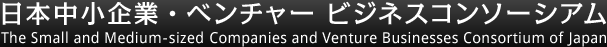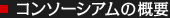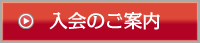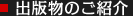開催日時: 2019年12月7日(土) 13時00分開始(12時30分受付開始)
会 場: 明治大学リバティタワー23階 サロン燦
*いつもの会場とは異なりますので、ご注意ください。
【報告会プログラム】
12:30~ 受付開始(リバティタワー23階 サロン燦入口)
13:00~14:00 坂本恒夫氏(福島学院大学)
「本年度のコンソーシアム賞に、この人を推薦します」
概要:福島部会において素晴らしい報告が行われ、感動のあまり、参加者一同、涙しました。その概要を報告します(生キャラメル付き)。
14:00~15:00 西本山海氏(大分大学大学院 経済学研究科 博士後期課程)
「Likertが提唱する人的資源会計と「討議資料 財務会計の概念フレームワーク」との整合性についての一考察」
概要:「討議資料 財務会計の概念フレームワーク(概念フレームワーク)」 は,企業会計(特に財務会計)の基礎にある前提や概念を体系化したものである。概念フレームワークは、将来の基準開発に指針を与える役割も有する。本報告では、概念フレームワークが提供する財務会計の概念を検討し、Likert(1967)が提唱する人的資源会計が、その概念に沿うものであるか探ることを目的とする。
15:00~16:00 森谷智子氏(嘉悦大学)
「オルタナティブ投資と証券化商品~日本の金融機関を巻き込む米国CLO~」
概要:2019年に入ると、メガバンクや農林中央金庫などがオルタナティブ投資の対象として、証券化商品、特に米国におけるCLO(CollateralizedLoan Obligation,ローン担保証券)への投資を積極的に行っていることが報道された。このCLOは、低格付け企業の貸付債権を裏付け資産として組成したものである。そのため、日本の金融機関の財務状況に影響を与えることになった。そこで、このようなCLOの行方はどうなるのかについて検討する。
16:00~17:00 正田繁氏(明治大学)
「グローバリゼーションと英語の罠」
概要:グローバリゼーションが進展する中で英語の重要性が強調されて久しい。しかし、英語教育や入試など、さまざまな問題点が指摘されている。こうした状況を鑑み、日本の英語教育のありかたについてビジネスの視点から考察する。
17:00~18:00 坂田淳一氏(桜美林大学)
「中小製造業における事業承継に係る支援課題の研究(中間報告)」
概要:事業環境の激変、経営者の高齢化が進む中、円滑な事業承継支援が重要な課題となっている。本研究においては、都内中小製造業1500社に書面調査を行い200社強から回答を得た結果及び、数社へのヒアリング結果を報告する。
18:30~ 懇親会(会場:明治大学リバティタワー23階 サロン燦)
参加費 部会参加費1,000円 懇親会費 3,000円